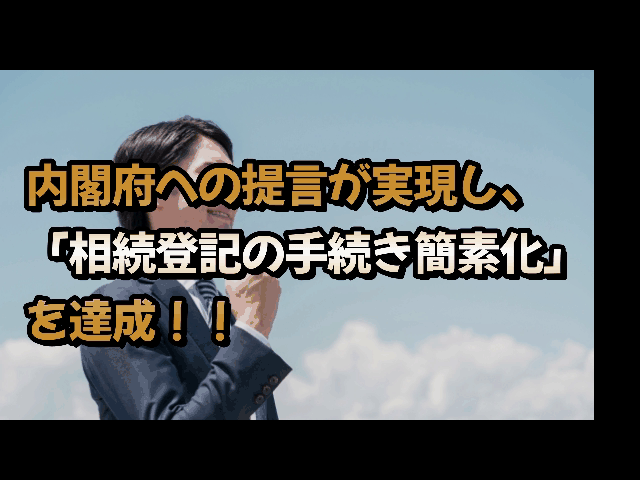内閣府「規制改革推進に関する答申」への提言が採用!!
内閣府所管の「規制改革推進に関する答申」において、
当事務所代表の井原による、相続手続きに関する提言が採用されました!!
①代表司法書士・井原による提言内容
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/archives/016/202210/regulatory_20221020.pdf
(一般社団法人信託協会「NEWS RELEASE」 令和4年10月26日 P8)
を簡単に言うと・・・
・不動産の相続による名義変更登記(以下、「相続登記」といいます)においては、不動産の所有名義人と、戸籍上亡くなったとされる方が同一人物なのか(同一性があるか)を証明する書類が必要。
・通常は、上記の証明書は「住民票」か「戸籍の附票」で足りる(不動産の所有名義人と、戸籍上の亡くなったとされる方の住所と氏名が一致すると、同一性があると扱われる)。まれに、住所や氏名が不一致となる場合、他に証明書類を付けなければならない。
・不一致となる場合で、所定の書類が添付できない場合は、「相続人全員の上申書(実印)」の提出が必要になる。ほかの相続人が納得していない場合は、折角遺言書があったとしても、納得しない相続人から上申書をもらうことが出来ないため、相続登記が進められないという問題が発生していたため、納税通知書などを利用し、より簡易な書類で同一性が認められるよう、要望を提出した。
②上記提言が採用されたことで、法務省より各法務局への通知がされました
当該提言は、代表の井原が前職(三菱UFJ信託銀行株式会社)の勤務時代に、
所属する相続部門を代表して、一般社団法人信託協会へ提出したものです。
信託協会の審査を通過した要望が内閣府へ提出され、その後管轄の省庁にて検討された結果、
特に「規制改革を行うことで、国民の利益になる」と判断されたものについて、通達等により各関係各所へ伝達されます。
司法書士としてのこれまでの経験が存分に生かされたものとして、国民の皆様の相続手続きの軽減に役立つてれば幸いです。
(おさらい)相続登記の義務化~令和6年4月1日スタート~
不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の名義変更登記(相続登記)の必要があります。
これまでは、相続登記は「不動産を売る」「誰が所有者かをはっきりとさせておきたい」といったような、
希望がある方だけが行えばよいというルールになっていました。
しかし今年の4月1日より、相続登記が義務化されることで、「やらなければいけないもの」となります。
例えば、地方などで代々同一の家族が不動産を承継しているような場合は、
暗黙の了解で、誰が後継ぎなのかはみんな知っていますので、
わざわざ手間と費用をかけて相続登記を行わないことも多くありました。
なぜ相続登記は義務化されたの?と疑問に思われる方もいると思いますので、こちらの記事でご確認ください。