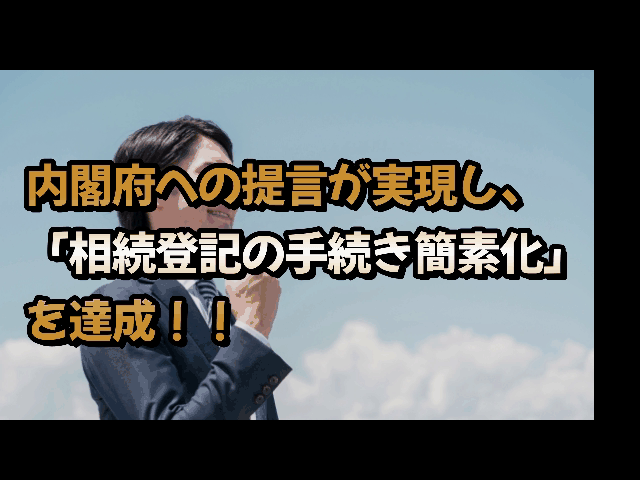と対象者
| 分かりやすさ | |
| 重要度 | |
| お役立ち度 | |
| 対象者 | 相続税の節税に興味がある方 |
生命保険を活用した相続税の節税方法とは?
相続税の節税対策をしたいものの、もしもの時に備えて現金は減らしたくない、、、
そんなお悩みのときは、生命保険を活用した節税方法を検討してみましょう。
生前贈与を利用して、子供にまとまった資金を渡してしまうと、ご自身の老後資金が不足するかもしれません。
一方で、生命保険は、ご自身が亡くなった時に渡せますし、仮に生きている間に急に現金が必要になった時には、
解約して解約返戻金を受け取ることが出来ます。
ただし、解約返戻金は一定期間をすぎないと、元本割れして極端に目減りしてしまうリスクもあるので注意が必要です。
生命保険のメリットとしては、保険契約者(被相続人)が亡くなった時には、指定された受取人に確実に死亡保険金を渡すことが出来ます。
更に相続税上では、受け取った保険金は「受取人の固有財産」として扱われて、遺産分割の対象にはなりません。
後で詳しくご説明しますが、これはつまり「相続人同士で話し合いをせずとも、自動的に特定の人に渡せる財産になる」ということです。
自宅など、分けるのが難しい財産を相続するときに、とても威力を発揮します。
さらに、死亡保険金は相続税の計算上も、基礎控除(3000万円+600万円×相続人)とは別に、
「法定相続人×500万円」分の非課税額を控除できます。
同じ額の現金を相続するよりも、相続財産の評価額を減らせる効果があるため、節税効果が発揮できます。
現金を残すと、全額に対して相続税がかかってしまうのに対し、保険金で渡す場合は、大幅な税金の節税が出来るということです。
保険を検討してみない手はないかもしれませんね(^^♪
生命保険を活用するメリット
● 亡くなった時に、すぐに現金(死亡保険金)で受け取ることが出来る(葬儀代や相続税の納税資金になる)。
● 受取人を指定する事が出来るので、相続人以外にも財産を残せる。
● 非課税部分が控除されるので節税になる。
生命保険の控除額の計算 = 法定相続人の数(※) × 500万円 (※)相続放棄をした人も含められる。
例)相続人が3名なら、500万円×3=1500万円の控除をうけることができる。
相続財産が「自宅」と「預金」の場合は、保険活用の検討を
遺産として、ご自宅と現金がメインとなる方は、生命保険を活用した相続対策を検討した方が良いでしょう。
なぜなら、ご自宅は相続人間で分けようと思っても、簡単に分けることが出来ず、一人の相続人が実家を相続したとすると、残りの現金だけでは、他の相続人の相続分に不足する可能性があるからです。
そうなると、多くのケースで「実家を一人で相続するのは不公平!!」という不満が出ます。
それで、仕方なく実家を相続人全員で相続しようとなるのですが、これはハッキリ言ってトラブルの元です。
誰か一人が「実家を売って分けよう」と言い出して、実際に売却活動を始めたものの、全員が納得する金額で売れなかったり、「実家は思い出があるから売りたくない」と言えば、いつまでたっても売ることが出来ません。
このように、ご自宅の相続は、とてももめやすい要素を持っており、生前にしっかりとした対策を取っておくことがとても重要です。
生命保険を活用した相続対策とは?
相続財産として、ご自宅がメインとなる方は、特定の相続人を受取人として、生命保険を活用した、代償分割(だいしょうぶんかつ)の準備が有効となります。
例えば、「実家は長男に守って欲しい」と考えた時、長男を受取人とする生命保険に加入します。
すると、長男は受け取った保険金を代償分割の為の資金にすることが出来ます。
代償分割とは??
=相続人の一人(または複数人)が遺産を取得する代わりに、他の相続人には相応の代償金を支払うという方法。
例えば、一人がご自宅を相続する代わりに、他の相続人には、自宅を相続した相続人から現金を渡すことで、曹宇族人間のバランスを図ろうとすること。
生命保険金を代償資金として活用する例

上記例の場合、母の相続財産は「自宅の家と土地で2500万円」と「現預金500万円」を合わせて3000万円です。
相続人は子供2名のため、法定相続割合は1/2ずつの1500万円となります。
仮に長男が自宅の家と土地を相続した場合、長男は現預金の500万円しかもらえず、法定相続分より1000万円少なくなってしまいます。

そこで、母は長男を受取人とする生命保険金1000万円に加入します。
その結果、この生命保険金は長男の固有財産となり、母が亡くなった際に、長男が受け取ることが出来ます。
長男は、自宅の家と土地の他、現預金500万円の全てを一旦相続したのちに、
代償分割として、長女に現金1500万円を渡します。
こうすることによって、長男と長女は、それぞれ相続財産から1500万円を受け取ったことになります。
相続人同士で揉めることを避けるためにも、母は生命保険への加入と一緒に遺言書を作成しておくと良いでしょう。
遺言書には「付言事項」と呼ばれる、ご自身の想いを残せる欄があり、そこでしっかりと「長男に家を守って欲しい。そのための保険金である。」などを記しておき、他の相続人が納得できるようにしておくことも大切です。

【クリックすると税理士紹介希望者募集【税理士紹介ネットワーク】へ移動】

【クリックすると【税理士ドットコム】へ移動】