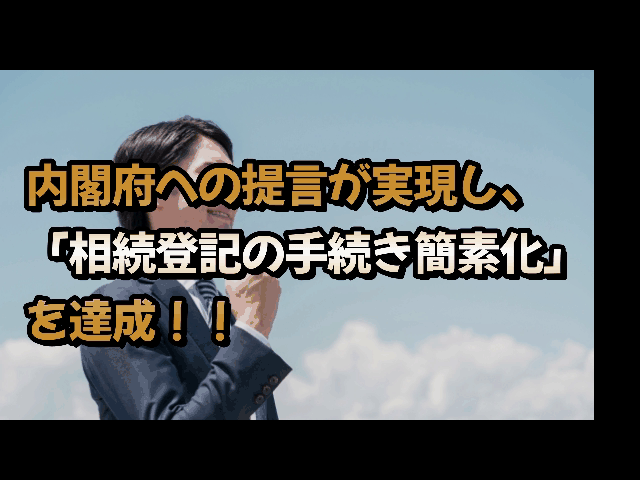と対象者
| 難しさ度 | |
| 重要さ度 | |
| お役立ち度 | |
| 対象者 | 相続手続きを依頼したいが、どこに依頼するか悩んでいる方 |
この記事では、相続手続きを専門家に依頼したいが、どこに頼めばいいか悩んでいる方に向けて解説していきます。
相続手続きは、一生に何度もあるわけではありませんし、役所や銀行周りは平日しか空いてないこともあって、ご自身で行うのは案外ハードルが高いと感じると思います。
そこで、専門家に依頼しようかと考え、インターネットで検索してみるものの、色々な専門家が代行サービスを行っていて、ご自身に最も適した専門家が分からない方もいるでしょう。
この記事は、そんなお悩みを持つ方の一助となればうれしいです。
相続手続き代行サービスを行う専門家の違いは?
こんな疑問を少しでも解決するために、現司法書士で、信託銀行でも相続サービスを持つ筆者が、疑問に回答します!
相続手続きの代行サービスとは?

相続手続き代行サービスとは、面倒な相続手続きを、依頼者に代わって行ってくれるサービスです。
具体的には、平日日中に役所や銀行を回って必要書類を集めたり、税務署や法務局などの難しい手続きを代行してもらうことができます。
また、財産分けのために身内同士で遺産分割の協議をする際にも、法律のアドバイスがもらえたり、客観的な目線で親身に相談にのってくれるところもあります。
自分たちだけでやろうとすると、一部の相続人から「公平性が保てない」などの声がでてしまうかもしれません。
相続手続きは専門的な用語が難しく、また期限も決まっているため、もし間違えてしまうと財産分与がスムーズに進まない可能性もあります。
大切な財産を上手く引き継ぐためにも、相続手続き代行サービスを活用するとよいでしょう。
サービスを提供している専門家や業者は?

相続手続き代行サービスを行っているのは、主に「司法書士・税理士・弁護士・行政書士(まとめて”士族と言います”)」か、もしくは「信託銀行(代表例はメガバンク系の信託銀行)」です。
司法書士や税理士などの士族は、難解な国家資格を突破し、法律や税務の最新知識にも精通した、いわゆる「相続のプロ」です。
それぞれの士族ごとに得意領域があります。司法書士であれば不動産登記、税理士なら税務申告といった「強み」を活かして、トータルで相続業務に取り組んでいます。
一方、信託銀行はというと、一般の方にはあまり馴染みのないかもしれませんが、一般の商業銀行(三菱UFJ銀行や三井住友銀行)と比べてやや専門的な業務を行っています。
信託銀行は、メガバンク系が多いこともあり、商業銀行の顧客層を利用して、主に法人向けに資産運用などを行っています。
個人向けサービスの一環として、最近は相続分野にも注力しており、遺言信託など様々な商品を発売しています。
信託銀行は、士族が行うような国家資格者が行う業務はできないため、お客様と士族をつなぐ役目を果たします。
特別な資格が無くてもできる業務(預金の調査や解約手続きなど)については、直接信託銀行が行っています。
| 相続サービスの提供者 | 特徴 |
|---|---|
| 司法書士・税理士などの士族 | 各々の専門性を強みに、最新の法律や税務にも精通した「相続のプロ」。 |
| 信託銀行 | 士族業務は行えず、士族の紹介のみ。その他の業務は自身でも行える。 |
| 商業銀行(一般の銀行) | 信託銀行の代理店。信託銀行へ顧客を紹介し、自身ではサービス提供はしない。 |
サービス提供者別のプラス面・マイナス面は?

サービス提供者として「士族」と「信託銀行(銀行含む)」の大まかな違いは、前章でご理解いただけたと思います。
次に、実際にどの提供者に依頼すればよいのかを考えるにあたって、士族ごとの「プラス面」と「マイナス面」、そして信託銀行との比較を行っていこうと思います。
士族は国家資格であり、法律によって「その業務を独占的に行うことが出来る」と定められています。
独占的とは「その業務はその士族しかできない」ということですので、非常に強力な資格であり、その業務こそが「プラス面」であると言えます。(裏を返すと、各士族の独占業務以外は行えないので、その点は「マイナス面」と言えます。)
比較の方法として、実際の相続手続きに沿って、どの士族が独占的に行うことが出来るのか、つまりは「各士族はどの手続きが得意なのか」という視点で解説していきます。
「相続手続きについて各士族が対応できる業務範囲」
| 司法書士 | 税理士 | 弁護士 | 行政書士 | |
|---|---|---|---|---|
| 相続人の調査 (戸籍謄本の収集代行) | ||||
| 相続財産の調査 (預金残高・不動産の所在等) | ||||
| 相続放棄の申立て | ||||
| 遺言検認の申立て | ||||
| 遺産分割協議書の作成 | ||||
| 不動産の名義変更 | ※1 | |||
| 預貯金の解約 | ||||
| 株式の名義変更 | ||||
| 自動車の名義変更 | ||||
| ゴルフ権・リゾート権の名義変更 | ||||
| 相続税の申告 | ※1 | |||
| 相続人間の紛争解決 | ※2 |
※2 認定司法書士の場合は、140万円以内の事案であれば対応可。
各々の士族で、得意分野が異なる(表の◎)ため、自身が最も解決してもらいたい相手を選ぶとよい。
比較表で「×」となっている項目は、依頼先によっては他の士族と連携して対応してくれる場合もある。
なお、信託銀行についても触れておきます。
信託銀行は、士族のような独占的業務というものはありません。
よって、相続手続きでは、各々の手続き上必要に応じて、各士族を紹介して対応しています。
つまり、手数料の面で言えば、「士族の手数料の全てが、別途発生する」ことになるため、最も割高になってしまうのはやむを得ないでしょう。
サービスの品質面でも、信託銀行ならではといったものは少なく、コスパ面では見劣りします。
「先代から付き合いがあるから」「相続後の資産運用の相談にのってほしい」といったような、銀行との長い付き合いを望むケースで、希望される方が多いのではないでしょうか。
まとめ
相続代行サービスの提供業者ごとの比較について、お分かりいただけたでしょうか。
私自身、実際に信託銀行で相続業務を行っていた時は、様々な士族をお客様にご紹介しながら、解決にあたっていました。
ただでさえ高い信託銀行の手数料に加えて、別々の士族の手数料が別途発生するので、総額費用はかなり割高になっていました。(信託銀行で扱うお客様は資産家の方が多いこともあって、あまり費用を気にされない方も多いのも事実です。)
各士族へ直接依頼する方が、余計な紹介費用がかからず、総額では割安になるのも当然です。
当事務所では、司法書士事務所の強みを発揮するとともに、他の士族とも強力な連携体制をとっており、費用も割安にてご提供しております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。
また、今回挙げた代行サービス業者の他にも、不動産業者の一部でも、相続した不動産の売却をご希望の方に向けて、各士族を紹介して「相続の窓口を一本化」に対応していますので、合わせてご紹介しておきます。
「相続の窓口」では、株式会社ネクサスプロパティマネジメントが運営しており、担当者がお客様の相続手続きに必要な士族(税理士、司法書士など)を手配してくれて、更には不動産の売却まで相談できます。
【クリックすると相続の窓口サイトへ移動】
基本的なサービス内容は当事務所と概ね同じですが、夜間対応や料金面で差があるため、「何を」「どこまでやってくれるのか」を問い合わせし、比較してみてはいかがでしょうか。
また、相続税がかかるかどうかが気になる方には、「税理士紹介希望者募集【税理士紹介ネットワーク】」「税理士ドットコム」といったサービスがあり、税理士など様々な専門家の紹介を行ってくれます。
相続税が心配な方、まずは税理士に話を聞いてみたい方は、こちらのサービスを利用してみてはいかがでしょうか。
【クリックすると税理士紹介希望者募集【税理士紹介ネットワーク】へ移動】

【クリックすると【税理士ドットコム】へ移動】