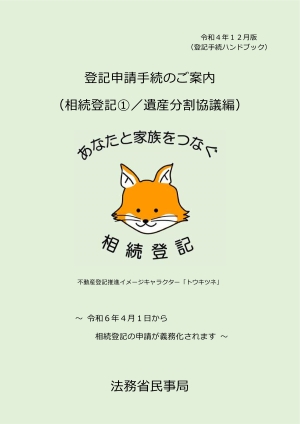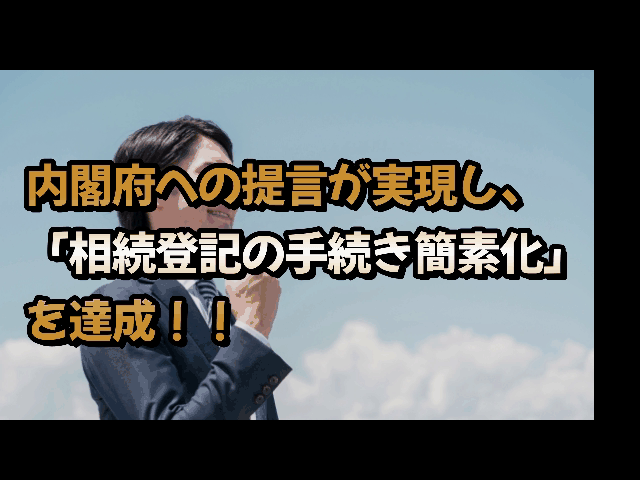と対象者
| 難しさ度 | |
| 重要さ度 | |
| お役立ち度 | |
| 対象者 | 不動産を相続した方で、今後の手続に悩んでいる方 |
大切な故人様がお亡くなりになった後、ご自宅などの不動産の手続きをどうしたらいいのかを解説しています。
相続人で話し合いはしたものの、その後の手続きをどうしたらいいのかわからない方向けの記事です。
不動産手続きの一歩目は、「遺言書」の有無!?
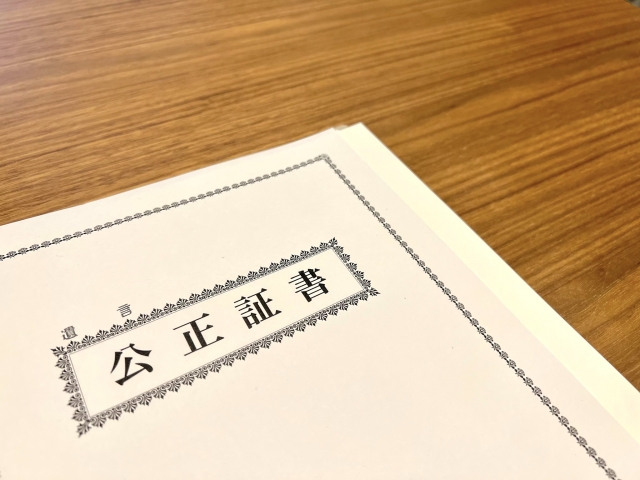
まず最初にやるべきことは、故人様が遺言書を残していたかどうかの確認です。
もちろん、遺言書を残していても、「どこにあるかわからない!?」ということでは、有効な手続きが行えません。
遺言書の探し方はこちらの記事を参考にしてください。
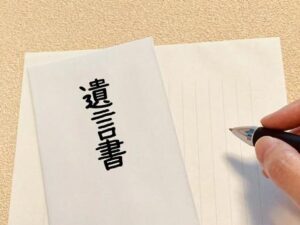
遺言書が見つかれば、原則として遺言書の内容に従って、記載された相続人が財産を取得することになります。
探したものの、結局遺言書が見つからなかった場合は、法定相続人全員で、誰がどの財産を取得するのかについて協議を行います。
協議の結果を「遺産分割協議書」という書面に記録し、全員の実印を押印することで、協議内容が有効となります。
ステップ①
まず最初に、【遺言書】を探す。
遺言書がある・・・遺言書の内容に従う。
遺言書が無い・・・法定相続人全員で話し合う。
不動産を相続したなら、自分自身への名義変更が必須

無事遺言書が見つかり、自分自身が取得者として記載されていたとしても、そのまま何もしなければ、他の人に対しては「自分が相続したんだ!」ということはできません。
自分自身が相続した事を、周囲にしっかりと示すためには、不動産の名義変更手続きが必要です。
また、相続税の納税のためなどの理由で、不動産を売却したい場合も、亡くなった方の名義のままでは売却することはできません。
不動産を相続したら、名義変更を必ず行う事。理由は次のとおり。
自分が取得した事を、周囲に主張できるようになる。
ステップ②
不動産の名義変更手続きを行う。自分でやるのか、誰かに頼むのかを決める。
・・・次の章へ
誰かに頼む・・・司法書士へ依頼する。
知り合いに司法書士がいない場合は、ご自身で探す必要があります。
主な探し方は次のとおりです。
- インターネットで検索する。
- 司法書士会連合会に連絡し、紹介を受ける。
- 既に、他の相談窓口(不動産業者、税理士、FPなど)と接点がある場合は、紹介してもらう。
手続ごとに窓口が違うのが面倒な方へは「窓口の一本化」がおススメ
お仕事や家事など、多忙のためご自身で司法書士を探すのを面倒に感じる方は、「相続の窓口を一本化」してくれるサービスの利用がおススメです。
「相続の窓口」では、株式会社ネクサスプロパティマネジメントが運営しており、担当者がお客様の相続手続きに必要な専門家(税理士、弁護士、司法書士など)を手配してくれて、更には不動産の売却まで相談できるため、自分自身で探したり、判断する手間が省けて便利です。
基本的なサービス内容は当事務所と概ね同じですが、夜間対応や料金面で差があるため、「何を」「どこまでやってくれるのか」を問い合わせし、比較してみてはいかがでしょうか。
【クリックすると相続の窓口サイトへ移動】
信託銀行に相続手続きを依頼する場合
故人様が残してくれた大切な資産を確実に相続するためにも、信託銀行等の専門機関に相続手続きを依頼すると、こうした面倒な手続きを一括して代行してくれます。
ただし、一般的に信託銀行は費用が割高(最低100万円~)となりますので、ご自身でしっかりと「どこまで代行してくれるのか」「追加費用は発生するのか」など依頼内容を確認してください。
当事務所では、元信託銀行員の目線で、信託銀行と同一のサービスを、低料金にて提供しております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。
相続税が気になる場合
相続税がかかるかどうかが気になる方には、「税理士紹介希望者募集【税理士紹介ネットワーク】」「税理士ドットコム」といったサービスがあり、税理士など様々な専門家の紹介を行ってくれます。
相続税が心配な方、まずは税理士に話を聞いてみたい方は、こちらのサービスを利用してみてはいかがでしょうか。
【クリックすると税理士紹介希望者募集【税理士紹介ネットワーク】へ移動】

【クリックすると【税理士ドットコム】へ移動】

不動産の名義変更手続きを自分で行うには!?

不動産の名義変更手続きを行うには、法務局という役所へ必要書類を提出します。
ご自身で手続きを行う場合、不動産の所在地を管轄する法務局へ出向きます。
ステップ③
名義変更手続きを自分でやる場合は、次の点に注意する。
・・・不動産所在地を管轄する法務局
必要な書類・・・法務省民事局のサイトで確認する。
また、手続き方法については、以下のいずれかの方法で調べることが出来ます。
①ご自身でインターネットで調べる方法
インターネット上には、様々な企業の情報が散乱していますが、最も内容が信頼出来るのは、「法務省民事局」が作成した、「不動産登記の申請書様式について」でしょう。
こちらは、遺言書の種類ごと(公正証書遺言、自筆証書遺言)に、手続き方法が詳細に記載されています。
遺言書が無い場合(遺産分割協議編)の手続の説明も、合わせてリンクを貼っておきます。
②役所の窓口で相談
①で必要書類を揃えたり、登記申請書を作成するのは、案外大変な作業です。
途中でわからなくなったり、作成してみたはものの不安のある方は、提出前に役所に出向いて相談する事が出来ます。
相談窓口は、東京法務局以外でも、各地域の法務局で相談窓口を設置していますので、インターネットで「(地域)+登記相談」と検索すると、該当ページをさがすことができます。
ただし、窓口での相談は、あくまでご自身で申請書の作成等を行う必要があり、役所の担当者が代わりに作成してくれるわけではありません。
ご自身で手続きを試してみても、完結が困難だとお感じになった場合は、当事務所へご相談頂くか、不動産名義変更の専門家や、各種紹介サービスへの問い合わせも検討してみてはいかがでしょうか。