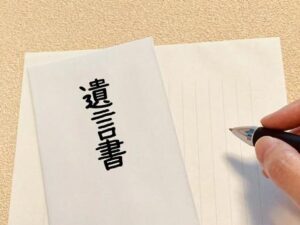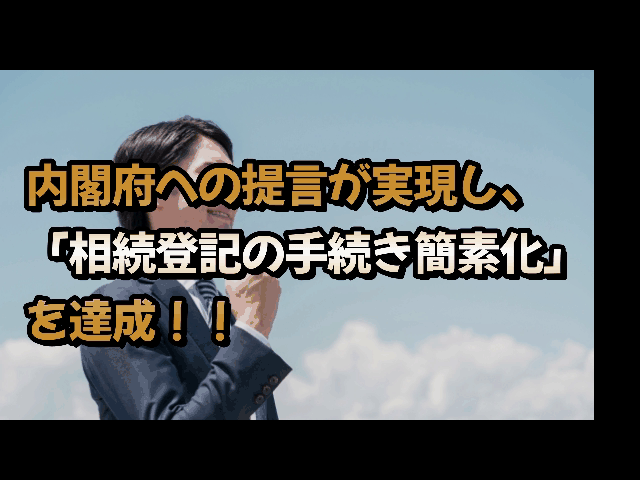と対象者
| 難しさ度 | |
| 重要さ度 | |
| お役立ち度 | |
| 対象者 | 預貯金を相続した方で、今後の手続に悩んでいる方 |
この記事では、故人様の預貯金口座の調査方法を解説していきます。
几帳面な故人様の場合、古いものまでずっとタンスの奥に保管されていて、丁寧に銀行ごとに束ねておられることもあるでしょう。
そこで通帳を開いてみると、記帳した最終日が数年前で止まっている・・・。
今現在は残高がいくらあるのか?
他にも口座を持っていた銀行があるんじゃないか?
こんな疑問が湧いてくるのではないでしょうか。
こんな疑問を少しでも解決するために、ここでは銀行預金の調査方法をお伝えします。
預貯金の調査方法のキホンをおさらい

預貯金の相続手続きの第一歩は、「故人様がどこの金融機関に口座を持っているのか」を把握するところから始まります。
通帳やキャッシュカードがある場合と無い場合で、探し方が違ってきます。
通帳・キャッシュカードが【ある】場合
故人様の遺品を整理する中で、預金通帳を発見した場合は、該当の金融機関のATMで記帳すれば、すぐに預貯金額を把握することが可能です。
※ただし、既に該当の金融機関側で故人様が亡くなった事を把握している場合は、口座が凍結されているため、ATMでの通帳記帳が出来ない可能性があります。
もしも預金通帳が見つからないときは、キャッシュカードだけでも構わないので探してみましょう。
もしキャッシュカードが見つかれば、その金融機関に必ず口座を持っています。
通帳があった場合と同様に、その金融機関に出向いて、ATMで残高を確認してみてください。

通帳・キャッシュカードが【ない】場合
通帳やキャッシュカードが見当たらない場合は、心当たりのある金融機関に問い合わせをします。
心当たりといっても、親がどこの銀行を使っていたかなんてわからないよ・・・、という方もいらっしゃるかもしれませんよね。
そんな時は、故人様のご自宅や勤務先の近く、またはよく行くスーパー等に設置されているATMなど、故人様が使っていそうな金融機関に口座を持っている可能性があります。
思い当たる金融機関の窓口に出向いて行って、「●●(故人様)の預金口座があるかもしれないので教えて欲しい。」と依頼してください。
※現時点では、相続財産の調査にあたって、全国の数多くある金融機関から故人様の口座すべてを洗い出す方法はありません。よって、ある程度の目星をつけて、口座の有無を調査していくことになります。
金融機関の窓口では、必ず「全店照会をしてほしい。」と伝えるようにしてください。
理由としては、たまたま出向いた金融機関の窓口(支店)に口座があればいいのですが、もし他の支店に口座を持っていた場合に、「こちらの支店では口座をお持ちではありません。」という、なんともつれない回答をされてしまう可能性があるためです。
金融機関の窓口担当(テラーさん)が、気が利く人であれば「他の支店も一緒に調べてみますね。」と言ってくれるのですが、忙しい月末などの場合、うっかり自分の支店だけしか調べてくれていなかった、という可能性もゼロではありません。
(銀行の支店は、月末などは特にバタバタしています。窓口時間も限られているため、テラーさんはとにかく忙しそうです。)

相続手続きでは、必ず「残高証明書」を入手
金融機関での調査は、必ず「残高証明書」を取得するようにしましょう。
残高証明書を取得することにより、故人様のご逝去された日時点での普通預金の残高はもちろんのこと、定期預金や投資信託など、その金融機関で故人様が保有していた財産の詳細を入手することが出来ます。
また残高証明書は、以後の相続手続きにおいて、客観的な資料として、とても重要なものとなります。
例えば、相続人間で遺産分割協議を行うにあたり、「どこの金融機関にいくらあるのか」示す資料になりますし、他にも相続税申告の計算にあたって、財産額や税額を算出する際にも使用します。
相続手続きでは、相続人が一人の場合を除いて、必ず他にも相続人がいます。
話し合いをスムーズに進めるためにも、客観的な資料は必ず残す様にし、無用な争いが起きない様に注意しながら進めていくとよいでしょう。
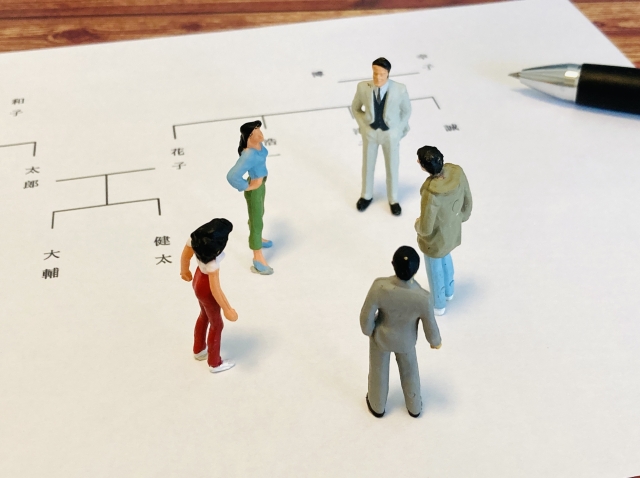
インターネット専業銀行(ネットバンク)の調査方法について

インターネット専業銀行(通称ネットバンク)の調査方法も、基本的には実店舗のある金融機関と同じです。
各金融機関のホームページに、「残高証明書」を請求する方法が書かれていますので、手順に沿って進めてください。
ネットバンクは通帳が無いことも多いため、故人様の財産調査の際に、調査から漏れてしまう事もあるかもしれませんので注意が必要です。
可能性として、故人様が生前使っていたパソコンやスマートフォンのお気に入りや、手帳などのメモ、郵便物(特に公共料金や保険料等の自動引き落としのお知らせ)などを念入りに確認するようにしましょう。
通帳が発行されない「ネット銀行」も、口座を持っていた可能性がある。
故人様のPCやスマホ、手帳、郵便物等を丹念に確認しましょう。
「公共料金や保険料等の自動引き落としのお知らせ」に、引き落とし口座がかかれていることも。
まとめ
預金手続は、それほど難しくは無いものの、平日日中に動かなければならない事も多く、また金融機関毎にやり方も違っていて、とても面倒な作業です。
故人様が残してくれた大切な資産を確実に相続する方法として、信託銀行等の専門機関に相続手続きを依頼すると、こうした面倒な手続きを一括して代行してくれます。
ただし、一般的に信託銀行は費用が割高(最低100万円~)となりますので、ご自身でしっかりと「どこまで代行してくれるのか」「追加費用は発生するのか」など依頼内容を確認してください。
当事務所では、元信託銀行員の目線で、信託銀行と同一のサービスを、低料金にて提供しております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。
また、信託銀行や当事務所の相続手続き代行サービスとの比較として、「相続の窓口を一本化」してくれる業者も合わせてご紹介しておきます。
「相続の窓口」では、株式会社ネクサスプロパティマネジメントが運営しており、担当者がお客様の相続手続きに必要な専門家(税理士、弁護士、司法書士など)を手配してくれて、更には不動産の売却まで相談できるため、自分自身で探したり、判断する手間が省けます。
【クリックすると相続の窓口サイトへ移動】
基本的なサービス内容は当事務所と概ね同じですが、夜間対応や料金面で差があるため、「何を」「どこまでやってくれるのか」を問い合わせし、比較してみてはいかがでしょうか。
また、相続税がかかるかどうかが気になる方には、「税理士紹介希望者募集【税理士紹介ネットワーク】」「税理士ドットコム」といったサービスがあり、税理士など様々な専門家の紹介を行ってくれます。
相続税が心配な方、まずは税理士に話を聞いてみたい方は、こちらのサービスを利用してみてはいかがでしょうか。
【クリックすると税理士紹介希望者募集【税理士紹介ネットワーク】へ移動】

【クリックすると【税理士ドットコム】へ移動】