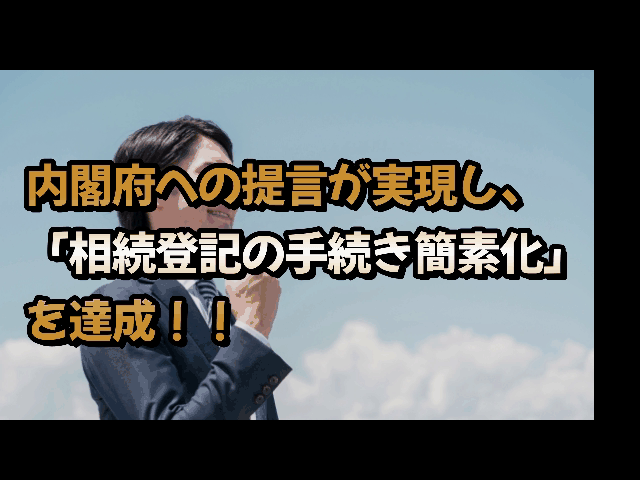と対象者
| 難しさ度 | |
| 重要さ度 | |
| お役立ち度 | |
| 対象者 | 美術品・骨董品・金を相続した方 |
この記事では、故人様の財産に「美術品」「骨董品」「金(ゴールド)」などがある場合の扱いについてわかりやすく解説していきます。
美術品等の財産は、生前に故人様から「これは高い買い物だった」と聞かされていた方も多いでしょう。
業者から査定見積をとってみたら、思った以上に高額だったなんてこともよくある話ですが、
そこで気になるのは「相続税」ですよね!?
「自宅に飾ってあるものだし、税理士さえ黙っていてくれればバレないんじゃないの・・・。」
なんていう、悪魔のささやきが聞こえてきてしまう事もあるかもしれません。
でも、税務署を甘く見てはいけません。もし後日見つかったら元も子もありませんよね。
当ブログは、「専門家が専門用語を使わず、やさしくわかりやすく相続を解説するブログ」です。
さあ、一緒に相続の勉強をしていきましょう!
美術品・骨董品・金(ゴールド)は相続税の対象になるの!?

相続税を計算する際、美術品等の財産は、相続税計算に加えなければならないのでしょうか?
これらの財産は、金銭で価値を見積もることが出来るため、「プラスの財産」として相続税の計算に加算しなければなりません。
他には、ゴルフ会員権や自動車、貴金属、宝石、そして知的財産権(特許権、著作権、実用新案権、意匠権、商標権など)なども、相続税の計算対象に含まれます。
金(ゴールド)が自宅金庫に保管してあった際に、
「自宅に置いてあって、特に名前が刻印されているわけでもないし、バレないんじゃないの?」と思うかもしれませんが、
購入金額が200万円を超える際には、購入時に身分証明書の提示が求められ、
更には業者から税務署へ「支払い調書」が提出されていますので、
万一税務署の調査が入った場合には、ごまかす事が出来ないと思っておいた方が良いでしょう。
仮に、200万円以下であったとしても、業者に対する税務調査が入った場合、業者に残っている購入記録を元に、
購入者が特定されてしまうので、やはり正直に申告した方が良いでしょう。
美術品などの評価額は専門の鑑定士に依頼する

実際に美術品などが相続遺産にあった場合、その評価額はどのように考えれば良いのでしょうか。
こうした商品は、値段があって無い様なもので、評価する人によって大きく金額が変わってくることもあります。
また、購入したときの額よりも大きく値上がり(値下がりの場合もあり)していることもあるので、
購入時の金額をそのまま評価額とすることもできません。
こうした場合は、しっかりとした鑑定士に鑑定を依頼し、「評価鑑定書」を発行してもらいましょう。
鑑定士に依頼して、財産の評価額を確認したい方は、こちらの業者もご検討下さい。
財産の評価額を把握したい方は、以下の業者も活用下さい。

評価額が5万円以下なら「家財一式」

鑑定士に評価してもらった結果、もし評価額が「5万円以下」の場合は、家電製品や家具などと同じ家財としてひとまとめにして「家財一式」として評価し、その金額を納税申告書に記載することが出来ます。
テレビやパソコン、タンスやソファー、洋服、靴、本、高価ではないアクセサリーやバック、楽器なども含まれます。
特に高価なものや、相続開始直前に購入したものを除き、通常は減価償却年数が過ぎて、評価額が5万円以内に収まるものが多いでしょう。
こうしたものを全てひっくるめて「家財一式」として、一般的には10万円~50万円程度で評価しておくとよいでしょう。
相続税を誤魔化そうとすると重い追徴金が発生することもある
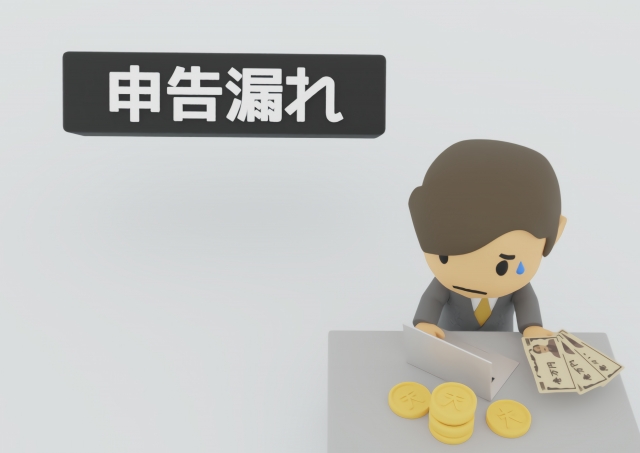
相続税の対象となる相続財産をワザと隠したり、ウソをついて相続税の支払いを逃れようとした場合は、
通常の相続税よりも、更に重い追徴金を支払わなければいけません。
相続税額を本来よりも少なく申告した場合、税務署に指摘される前か後かで、追徴金の支払いが変わってきます。
| 税務署からの指摘の前後 | 延滞税 | 過少申告加算税 |
|---|---|---|
| 指摘前に、自主的に修正申告を行った場合 | 年2.4~年8.7% | 無し |
| 指摘後に、修正申告を行った場合 | 年2.4~年8.7% | 年10%~15% |
相続税が気になる方は、このタイミングで税理士へ相談を
相続財産の評価を考えるにあたり、相続税が気になる場合は、この時点で税理士への依頼を検討した方がよいでしょう。
相続税は、財産評価額に応じて納税額が変わってきます。
また、もらう人が妻や夫など配偶者の場合は税金が安くなったりと、様々な控除が受けられます。
そうした相続税の制度を踏まえた上で財産の配分を決めることで、税理士への手数料を支払う以上に、税金を安く済ませる事も可能です。税理士費用は、そのためのアドバイス料と割り切ってもよいでしょう。
税理士側でも、財産内容の確認作業や相続人への聞き取りなどに時間を要しますので、依頼を検討する場合は早め早めに動いておくと、税理士からもより良いアドバイスをもらうことが出来ます。
もしもお知り合いに税理士がいない場合、もしくは相続税がかかるかどうかが気になる方には、依頼者に最適な税理士を紹介してもらえるサービスがあります。
相続税が心配な方、まずは税理士に話を聞いてみたい方は、こちらのサービスを利用してみてはいかがでしょうか。


相続税の申告と納税には期限があります(10か月以内)
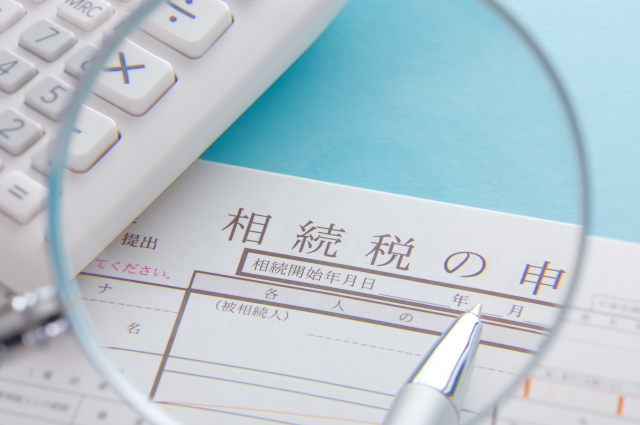
相続人が相続する遺産が確定したら、故人の亡くなった日から10か月以内に、相続税の申告と税金の納付をしなければなりません。
この期限までに、話し合いが出来なかった場合は、一旦は「未分割(みぶんかつ)」という形で、相続税の申告と納税を行います。
後日、話し合いが済んだ段階で、改めて申告をやり直します。
もしも、当初の未分割での申告よりも納税額が少なく済んだ場合には、払いすぎた相続税は戻してもらうことが出来ます。
払いすぎた相続税を取り戻すことを、「更生(こうせい)」といいます。
ただし、申告期限から5年以内に行わなければならないので、注意が必要です。
まとめ
故人様の財産の中に、美術品や骨董品などがあった場合の対応方法はお分かりいただけたでしょうか?
相続手続きは平日日中に動かなければならない事も多く、また役所や機関ごとにやり方も違っていて、とても面倒な作業です。
故人様が残してくれた大切な資産を確実に相続する方法として、信託銀行等の専門機関に相続手続きを依頼すると、こうした面倒な手続きを一括して代行してくれます。
ただし、一般的に信託銀行は費用が割高(最低100万円~)となりますので、ご自身でしっかりと「どこまで代行してくれるのか」「追加費用は発生するのか」など依頼内容を確認してください。
当事務所では、元信託銀行員の目線で、信託銀行と同一のサービスを、低料金にて提供しております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。
また、信託銀行や当事務所の相続手続き代行サービスとの比較として、「相続の窓口を一本化」してくれる業者も合わせてご紹介しておきます。
「相続の窓口」では、株式会社ネクサスプロパティマネジメントが運営しており、担当者がお客様の相続手続きに必要な専門家(税理士、弁護士、司法書士など)を手配してくれて、更には不動産の売却まで相談できるため、自分自身で探したり、判断する手間が省けます。
基本的なサービス内容は当事務所と概ね同じですが、夜間対応や料金面で差があるため、「何を」「どこまでやってくれるのか」を問い合わせし、比較してみると良いでしょう。