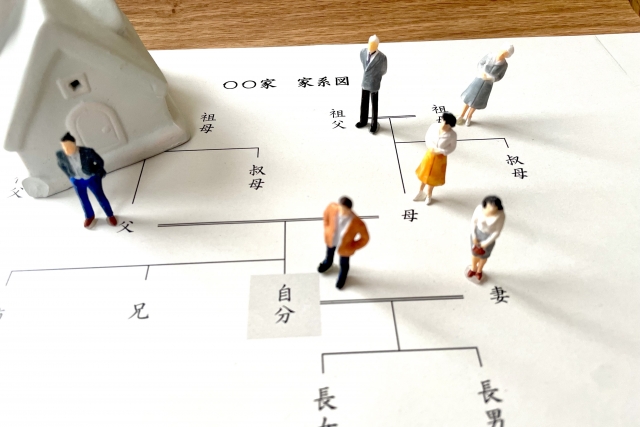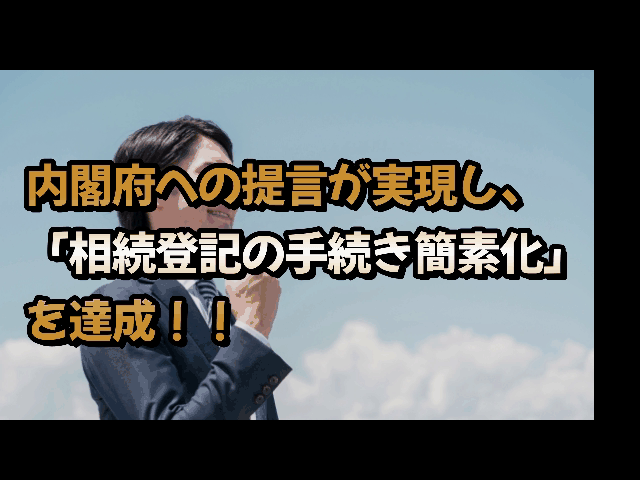と対象者
| 難しさ度 | |
| 重要さ度 | |
| お役立ち度 | |
| 対象者 | 故人のお世話をしていた方、会社を成長させた方 |
この記事では、故人様の生前に介護やお世話をしていた方や、故人の会社を大きく成長させた方が、
法定相続人ではないものの、遺産相続をもらえないかと悩んでいるケースについてわかりやすく解説していきます。
故人が遺言書を残していれば、こうした方へを遺産を渡すこともできたのですが、
遺言書が無い場合は、遺産を相続する権利は「法定相続人」にしかありません。
「なんでこんなに頑張ってお世話したのに報われないのか!?」何か手はないのか?
そんな方に読んでいただければ幸いです。
当ブログは、「専門家が専門用語を使わず、やさしくわかりやすく相続を解説するブログ」です。
さあ、ご一緒に勉強していきましょう!
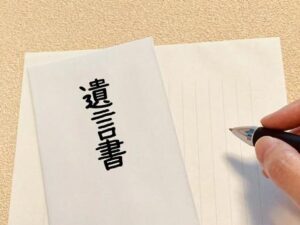
民法改正で可能となった「特別寄与料」制度とは!?

遺産分割協議で揉めることが多い案件として、親が亡くなった時に、ある相続人が「自分だけが親の面倒を看てきたのだから、財産を多くもらいたい。」と要求するケースです。
元々民法では、こうした療養看護や家業の手伝いを通じて故人の財産形成に貢献した場合に、
「法定相続人」であり、かつ貢献が「無償」であった場合に限り、
その相続人に対して、法定相続割合を超える財産が取得できるという制度がありました。
これは、従来より「寄与分」と呼ばれています。
これに対して、2019年の民法改正によって、上記の「法定相続人」のみが請求できる、という要件が緩和され、
長男の嫁といった立場の方も、遺産相続を請求できるようになりました。
立場が広がったため、名称も「特別寄与料」に変更されたということです。
ただし、請求できる人は誰でもよいわけではなく、一定の範囲の方に限られています。
特別寄与料を請求できる人
6親等内の血族(血族とは、血のつながりのある親族のこと。いとこの孫までが対象。)
3親等内の姻族(姻族とは、自身の配偶者の血族のこと。甥や姪までが対象。)
事実婚や内縁関係といった、戸籍上の親族ではない場合は適用できません。
また、介護等を「無償」で行っていたという点は変更ありません。
特別寄与料として認められる相場は幾ら位か?

特別寄与料の計算方法については、当事者間で合意ができるのであれば、自由に決めて構いません。
ただし、特別寄与料の金額は「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額」を超えることはできないとされています。
??ですよね。
もう少しわかりやすく言うと、次のとおりです。
「①故人が持っていた財産額」ー「②遺言書で第三者へ遺贈すると決められた金額」> ③特別寄与料
つまりは、「②第三者へ渡す分は、しっかりと確保しなさい。」「そこから、②を引いた額の範囲内で、③特別寄与料を決めなさい」ということです。
では、具体的にどれくらいを請求することが出来るのでしょうか。一般的な相場は次のとおりです。
①療養看護型(故人の看護をした場合)
基本的には、寄与料=介護日数×介護報酬相当額×裁量割合という計算式で考えます。
【介護日数】
入院期間・施設入所期間・介護サービスを受けた期間は原則として除きます。
【介護報酬相当額】
基本的には、介護保険制度で要介護度に応じて定められている介護報酬基準額によります。
個別的事情にもよりますが、概ね1日5000円~8000円程度が目安です。
【裁量割合】
親族には扶養義務があるため、介護等の専門家ではないことから費用を控えめに計算され、0.5~0.9を乗じます。
実務的には、0.7が採用されることが多くなっています。
例えば、介護日数が200日、介護報酬相当額が1日5000円、裁量割合が0.7の場合、寄与料は70万円となります。
②家業従事型(故人の事業に従事した場合)
一般的には、特別寄与者が通常得られたであろう給与額 ×(1-生活費控除割合)×寄与期間という計算式で考えます。
【特別寄与者が通常得られたであろう給与額】
賃金センサス(厚生労働省が発表する「賃金構造基本統計調査」のこと)という統計資料を参考に、
同種同規模同年齢の年間給与額を算出することが多くなっています。
【生活費控除割合】
家業の労働に対する報酬を受け取る代わりに、生活費の支出が免除されている事も多くあるため、その分を控除します。
以上が、特別寄与料の一般的な相場の考え方です。
特別寄与料は、法律で認められた権利ですので、要件を満たしている方は、他の相続人に対して要求しましょう。
請求には具体的な証拠を提示しましょう
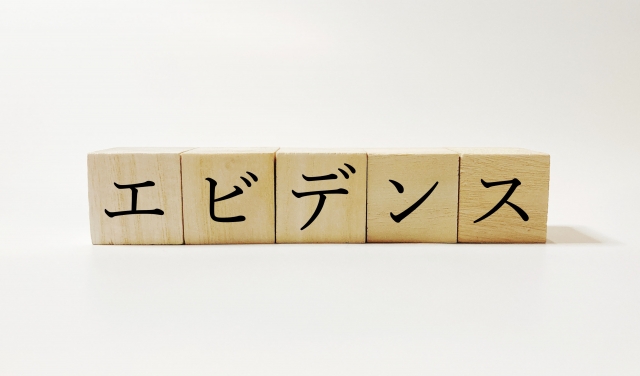
介護や家業によって、特別に寄与したと考えている方が、相続人に対して請求する場合、具体的な証拠を提示しましょう。
例えば、介護日誌や領収書など、故人の看護を実施した日数や程度、立て替えた費用などが分かる客観的な資料をあらかじめ準備しておくとよいでしょう。
その上で、介護報酬表などを利用し、プロの介護士に依頼した場合の費用を計算して、それを元に具体的な金額を提示するとよいでしょう。
もし請求が拒否されてしまったら家庭裁判所へ申立てを
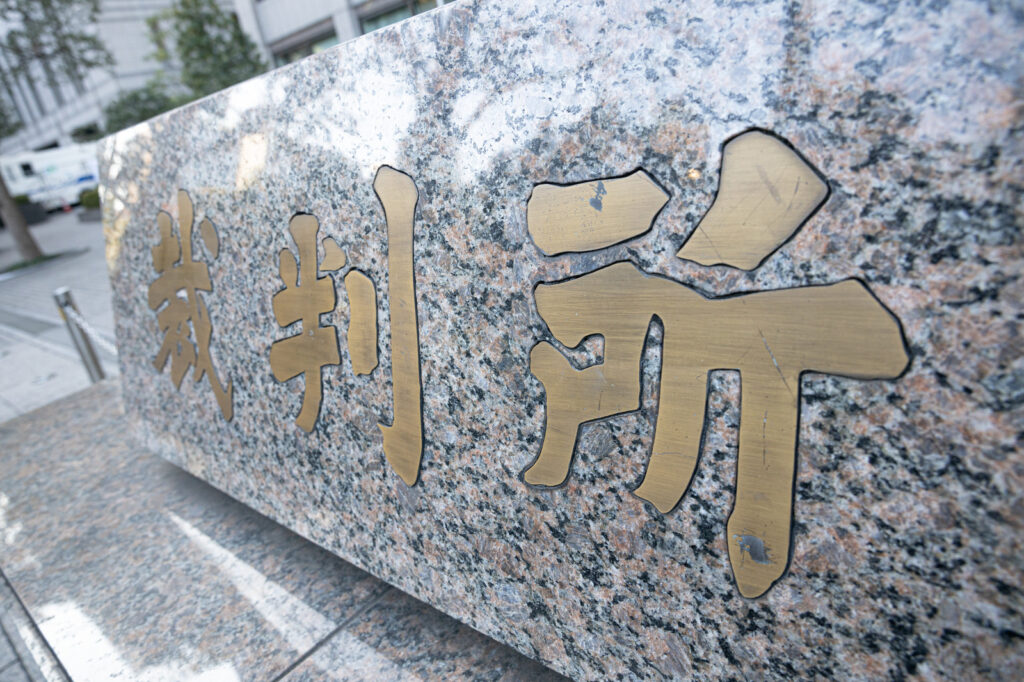
証拠を元に、特別寄与料を求めたとしても、他の相続人が認めてくれなかった場合は、
家庭裁判所に申し立て、調停又は審判の手続を利用することができます。
調停手続とは,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出するなどして、
裁判所が当事者から事情をよく把握したうえで,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をしたりして,
合意を目指した話合いを進めいていく手続きです。
もし調停手続で話合いがまとまらず,調停が不成立となった場合には,審判手続が開始されます。
※ 令和元年7月1日より前に開始した相続については,この申立てはできません。
なお、特別寄与料の裁判所への請求期限は故人が亡くなってから6ヶ月以内となっていますので、
当事者間での話し合いがうまくいきそうにない場合は、早めに裁判所への請求を検討した方が良いでしょう。
特別寄与料には相続税がかかります

特別寄与料を受け取った方へは、相続税の納税義務が生じる可能性があります。
相続税の申告期限は、故人が亡くなってから10か月以内となっています。
10か月以内に特別寄与料の金額が確定しないと、相続税申告にも影響が生じますので、
他の相続人の方も「他人事」と考えずに、速やかに協議を行うとよいでしょう。
相続税が気になる方は、このタイミングで税理士へ相談を
財産の配分を決めるにあたって、相続税が気になる場合は、この時点で税理士への依頼を検討した方がよいでしょう。
相続税は、もらう財産に応じて納税額が変わってきます。
また、もらう人が妻や夫など配偶者の場合は税金が安くなったりと、様々な控除が受けられます。
そうした相続税の制度を踏まえた上で財産の配分を決めることで、税理士への手数料を支払う以上に、税金を安く済ませる事も可能です。税理士費用は、そのためのアドバイス料と割り切ってもよいでしょう。
税理士側でも、財産内容の確認作業や相続人への聞き取りなどに時間を要しますので、依頼を検討する場合は早め早めに動いておくと、税理士からもより良いアドバイスをもらうことが出来ます。
もしもお知り合いに税理士がいない場合、もしくは相続税がかかるかどうかが気になる方には、依頼者に最適な税理士を紹介してもらえるサービスがあります。
相続税が心配な方、まずは税理士に話を聞いてみたい方は、こちらのサービスを利用してみてはいかがでしょうか。
【クリックすると税理士紹介希望者募集【税理士紹介ネットワーク】へ移動】

【クリックすると【税理士ドットコム】へ移動】

相続税の申告と納税(10か月以内)
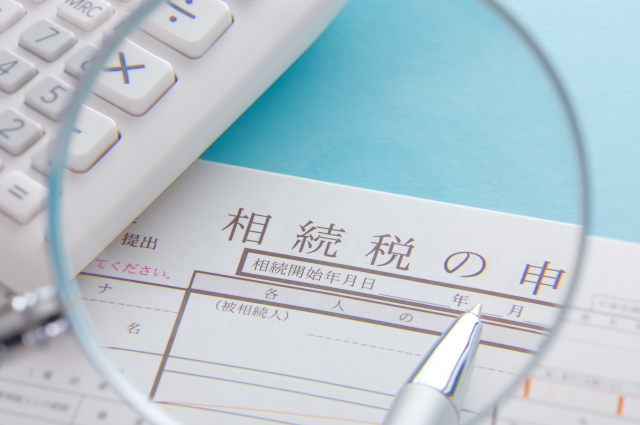
相続人が相続する遺産が確定したら、故人の亡くなった日から10か月以内に、相続税の申告と税金の納付をしなければなりません。
この期限までに、話し合いが出来なかった場合は、一旦は「未分割(みぶんかつ)」という形で、相続税の申告と納税を行います。
後日、話し合いが済んだ段階で、改めて申告をやり直します。
もしも、当初の未分割での申告よりも納税額が少なく済んだ場合には、払いすぎた相続税は戻してもらうことが出来ます。
払いすぎた相続税を取り戻すことを、「更生(こうせい)」といいます。
ただし、申告期限から5年以内に行わなければならないので、注意が必要です。
まとめ
故人様の財産に対する特別寄与料についての解説はお分かりいただけたでしょうか?
相続手続きは平日日中に動かなければならない事も多く、また役所や機関ごとにやり方も違っていて、とても面倒な作業です。
故人様が残してくれた大切な資産を確実に相続する方法として、信託銀行等の専門機関に相続手続きを依頼すると、こうした面倒な手続きを一括して代行してくれます。
ただし、一般的に信託銀行は費用が割高(最低100万円~)となりますので、ご自身でしっかりと「どこまで代行してくれるのか」「追加費用は発生するのか」など依頼内容を確認してください。
当事務所では、元信託銀行員の目線で、信託銀行と同一のサービスを、低料金にて提供しております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。
また、信託銀行や当事務所の相続手続き代行サービスとの比較として、「相続の窓口を一本化」してくれる業者も合わせてご紹介しておきます。
「相続の窓口」では、株式会社ネクサスプロパティマネジメントが運営しており、担当者がお客様の相続手続きに必要な専門家(税理士、弁護士、司法書士など)を手配してくれて、更には不動産の売却まで相談できるため、自分自身で探したり、判断する手間が省けます。
【クリックすると相続の窓口サイトへ移動】
基本的なサービス内容は当事務所と概ね同じですが、夜間対応や料金面で差があるため、「何を」「どこまでやってくれるのか」を問い合わせし、比較してみてはいかがでしょうか。